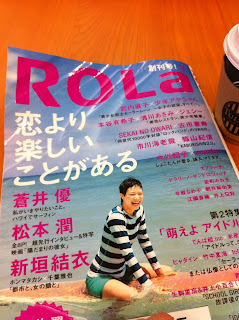Une nouvelle amie by François OZON /『彼は秘密の女ともだち』
アメリカで同性婚が認められましたね。 ⇒ 全米で同性婚“合法化”へ 米連邦最高裁が判断 @NHKニュース via cinematoday.jp そんなきょう、フランス映画祭で フランソワ・オゾン監督 の新作 『 彼は秘密の女ともだち(Une nouvelle amie) 』 を観てきました。 ものがたりはひとりの女性の死ではじまります。 レズビアンと言われてしまえばそれまでだけど、友情を超えた女ともだち、 ローラとクレール。 ローラの死が、夫、親友クレール、そしてクレールの夫ジルの日常を変えてしまいます。 女装、性的倒錯、出産や子育て、理性や世間体。 本当の幸せとは…? 自由に生きる、とか簡単にいいますが、「自由」を得るために闘わなければいけないし、個人の幸せと家族の幸せが常に同一項とは限らない。 LGBTについて話すとき、日本ではよくゲイ、レズ、バイが対象になっているような気がします。 ただ、実際はもっと複雑で、曖昧なものなんだろうな、と思います。 さすがフランス、そういった非合理的な “人間” を美しく、深く、そしてエスプリたっぷりに描いていました。 via cinematoday.jp 原題は Une nouvelle amie 。 直訳だと、新しい女友達、となります。 結局、主人公は人生の伴侶として最愛の友達を 選びました。 ただ「付き合う」、「一緒にいる」ではなく、「結婚」。 契約であり、法的な権利を有するものであり、社会への承認行為でもあります。 アメリカの連邦最高裁判所により 裁判命令書 には以下のようにあります。 No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. (人と人のさまざまな結びつきの中で、結婚以上に深い結びつきが...